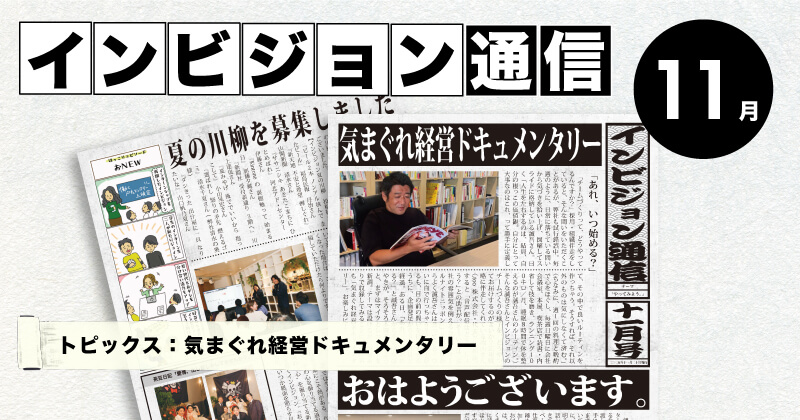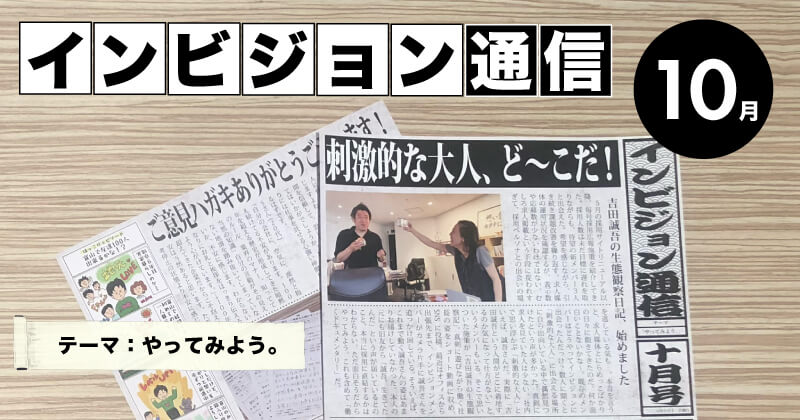メンバー

人生はサメになるためのプロセス
インビジョン入社前の経歴
サメと出会う前、出会ってから。
私の幼少期は、人前に出ることが苦手で自分の意見を発言することが少なかった。反面、昔から自分の世界に浸ることや自然と触れ合うことは得意だった。
高校時代の部活で軽音部に入部した辺りから、人前で表現することの楽しさを覚え、美術大学へ進学する。
美術大学では、自己表現をするために内省する必要があった。しかし、入学当初は自己表現をするための原動力になる核など無く、周りの同級生と比べると熱量は低かったし、自分の言葉や意思で表現できないことが恥ずかしいと思っていた。上手く表現できない苦しさはあったが、それでも、美術という分野が社会の中で一番魅力的だった。気が付けば、大学、大学院と進学し、修了後は大学の研究室の助手を務め、その後も非常勤講師や講座の講師など、インビジョン入社前は教える仕事をしていた。
私の核となる「サメ」と出会ったのは大学三年生の時。サメにどハマりし、ひたすらサメのことについて調べ、サメと人との関係性について考えることが始まった。
「サメ」とは未知な存在で、探っても探っても答えが見つからない、新しい知見が次々と出てくるという、どんなに熱しやすく冷めやすい私ですら思考を止めることができない摩訶不思議な存在であった。
そして「サメ」は私の創作のテーマになり、いつしか人生のテーマにもなっていった。
ちょうどその時、今までの人生には無かった自身にとって強いテーマが出来たからなのかもしれない。教える仕事は嫌いではなかったが、いつしか自分が美術において誰かに何かを教えられるものが無いかもしれないと思うようになる。自分にできることで、もう少し広い社会という環境を見る必要があると考え出したのもちょうどこの頃。
インビジョンに入社した理由
サメ対人ではなく、人対人。
当時のインビジョンには「制作」という役割でアルバイトの募集が出ていた。写真の修正や加工など、求人広告にまつわる制作の仕事だった。
美術という分野から少し離れた環境で自分のできる仕事を探していた私だが、美術や文化分野以外でほとんど仕事をしたことがなかったのだ。
面接時にポートフォリオが必要だった。しかし私は、デザイナーでもイラストレーターでもなかった。そのため、制作仕事の実績などなく、自身の創作活動で作ってきた作品のポートフォリオしか持っていなかったのだ。しょうがないので、作品しか載ってないポートフォリオを提出する。作品にも写真加工などの技術は応用していたため、私の能力を図るものさしになれば良いと思っていた。
最終面接で直接、代表の誠吾さん、ちなさん、三浦さんとお話ししてもらうことに。ポートフォリオについては大きく触れられることはないかもしれないと内心思っていたのが、まさかの「サメ、かっこいいね」の一言。私の作品そのものや制作し続けてきた過程など、人となりをポートフォリオから読み取ってくれたことに正直驚いた。それに、私の作品は万人受けするものでもなかった。むしろ好まれないことの多い表現もあったため、作品に対してフィードバックをもらうなんて予想もしていなかったのだ。
今振り返っても、何度振り返っても、インビジョンに入社した理由は、やはり代表の誠吾さん、ちなさん、三浦さんたちが、ちゃんとその人の熱量や想いや中枢に持っている大事にしているものに向き合ってくれたからだと思う。昔からインビジョンが大切にしている「本質的な人との繋がり」は、ちゃんと人と向き合うことだと思う。そんな人たちに出会えた私は、とても幸運だ。
入社後の光と影
想いをカタチに、パリにも行ってみた。
再度繰り返しになるが、入社前は「制作」という役割で写真の修正や加工など、求人広告にまつわる制作の業務が私の業務になるはずだと思っていた。
だがしかし、現実は違った。今はなき「デジタル図工部」という、デジタルと工作要素を組み合わせたクリエイティブチームが発足されたのだ。(もちろんチームといっても当時は私しかいない。)
「デジタル図工部」では工作という言葉がキーワードになる。コマ撮りアニメーションを作ったり、当時新卒採用のコンテンツとしてあった、学生が会社の社長とカフェで気兼ねなく話せるという「フライデーカフェ」に応募してくれた学生と一緒に動画撮影をしたりと、とにかく内容は様々だった。そして大概、材料も道具も何もない1から作ることが多かったのだ。まさに、子供番組によくある身の回りのものを使って作る工作番組のようだった。(一緒に動画を作った当時学生だった彼は、今でもインビジョンメンバーである)
しかし、デザイナーでもイラストレーターでもない私にとっては、実はとてもやりがいのある仕事だった。私にとって何もないところから作っていくことは、まさに「想いをカタチに」する作業だった。
美術分野から離れインビジョンで働き始めてから早や5年程経ったある日、「パリで1年間滞在制作ができる」パリ賞というチャンスをゲットすることができた。
私はインビジョンで働きながら自身の創作活動を続けていたため、これまでも幾度となく仕事と制作のバランスを図るためにスケジュール調整などでわがままを聞いてもらってきた。しかし今回は今までと訳が違って、1年間日本に居ないという大きな問題があった。インビジョンを辞めざるおえない、そんな覚悟で誠吾さんに報告と相談をする。
誠吾さんからの返事は「パリ賞?なにそれ、すごいじゃん、おめでとう!インビジョンパリ支局発足だね。」鳩が豆鉄砲を食らうとは正にこの状況。日本では駿河湾の海底峡谷、世界ではマリアナ海溝くらい、深い心意気なお言葉を頂き、私はインビジョンを辞めずに済んだのだ。そしてパリに向かった。
パリから無事帰国し、引き続きインビジョンで働かせてもらっている。
インビジョンで働いてから、「想いをカタチにする」ことは実体験が重要である、事をパリから戻ってきてまた振り返る。
デジタル化が進む中で、仕事でも創作でも人間味があるものを作れるのは人間だけ。自ら体験してきた事実が人間である証拠で、人間らしさを思う存分発揮して、「想いをカタチに」にすることがこれからもクリエイティブミッションであり、インビジョンの世界観を表現するのに欠かせないだろう。
エネルギーの源泉
サメになるためにも
最近思うことがある。何事も一人でできることは限られている。誰かの力、誰かの想いがないとカタチにはならないということ。
インビジョンの志である「働く幸せを感じるかっこいい大人を増やす」に共感する本質的な人のつながりは、チーム力になり、コミュニティになる。その集いが何をするにも大切だ。
サメは成長する都度、木と同様に脊髄の骨に年輪が刻まれる。年輪を数えることでサメの生きた年数が読み取れるのだ。
人も年輪と同じように成長する都度人生のレイヤー層が増えていく。
私の人生はサメになるためのプロセスで、そのプロセスには、サメと人間の関係性について考えることが欠かせない。歴史上人間がどのようにサメを捉えてきたのか、人間が関わるものとの関係性をどうのように構築していったのか、人間の年輪に当たる人生のレイヤーの一つである関係性の構築も読み解く必要があるのだ。
「本質的な人のつながり」は一人では生きていくことができない、人間の生存戦術だと思う。
「本質的な人のつながり」と常に向き合ってるインビジョンで働くことは、巡り巡ってサメになるためのプロセスとなる、かもしれない。
心が動くモノ・コト108
- サメ
- 自然
- 海
- サメ皮
- 楯鱗
- 魚皮
- 表皮
- バイオミメティクス
- 養殖魚
- アイスランド
- マス
- 粘度細胞
- 保水・保湿
- ケレシス
- コラーゲン
- 軟骨
- おろし金
- 革製品
- 地面
- 砂
- 砂利
- 泥
- 粘土
- 泥漿
- 釜
- 土
- 腐葉土
- 赤土
- 釉薬
- 陶器
- 陶芸
- セラミック
- 型
- 屋上庭園
- ランドスケープ
- 菜園
- 鉢
- 植物
- 種子
- コンポスト
- ラテックス
- 羊
- 羊毛
- 毛糸
- 編み物
- ニット
- ニッター
- 綿
- 絹
- 麻
- 共用庭園
- コミュニティガーデン
- 小屋
- 養蜂
- 鉛筆で描くこと
- ペンで描くこと
- 筆で描くこと
- 筆で塗ること
- 刷毛で塗ること
- 切ること
- 削ること
- 練ること
- 磨くこと
- 組み立てること
- 貼ること
- 付けること
- 流し込むこと
- 混ぜること
- 打つこと
- 叩き込むこと
- 成形すること
- なぞること
- 平すこと
- 塗り込むこと
- 接続すること
- 炙ること
- 彫ること
- 写すこと
- 乾燥させること
- 色を作ること
- 燻すこと
- 焼くこと
- 覚すこと
- 剥ぐこと
- なめすこと
- 穴を開けること
- こねること
- 洗うこと
- リサーチすること
- 計画すること
- 説明すること
- 共同者を集めること
- チームを作ること
- 役割分担すること
- 先人に話を聞くこと
- 得意分野ごとに頼ること
- 行動すること
- 企画すること
- 協力者を集めること
- 準備すること
- お願いすること
- 宣伝すること
- 制作すること
- 設営すること
- 運営すること
- システム化すること
- 続けること
- また再開すること