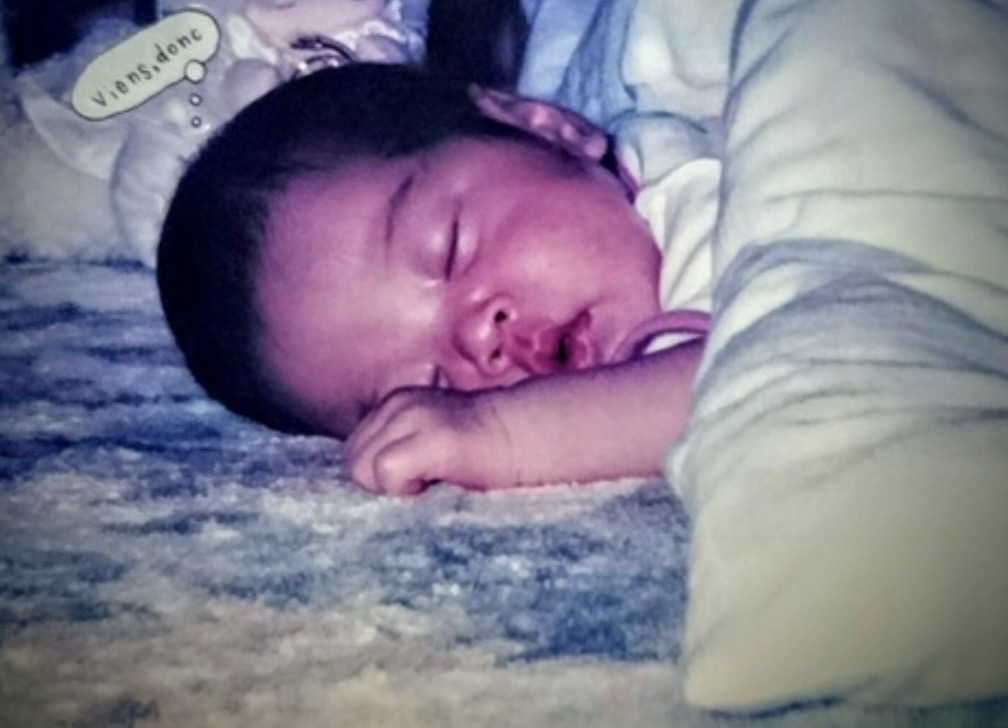道徳と合理、文明と文化、違いに出会う面白み

先日、とある取材のなかで朱子学の話題が出て、思いがけず驚かされました。
ちなみに私の朱子学リテラシーはごく一般的で、
の4段階でいうと「3.なんとなくイメージはある」程度。コラムのテーマも朱子学そのものではないので、とっつきやすい内容だと思います。
崇高な道徳の正体は、徹底した合理だった
話を戻すと、取材の流れで話題は自然と組織論から朱子学へ移りました。
私のなかで朱子学は「道徳教育の源」のようなイメージが強く、忠実や誠実といった、人の在り方として崇高な言葉が思い浮かぶものでした。ところが、「その本質は人を合理的に統治するための仕組みにある」という話になり、「ウッソー!」と驚かされました。気になり調べると、夫婦の立場や役割まで細かく規定され、「民族を骨の髄まで思想化する学問」とまで表現する本もある。もし今の自分に適用されたら、3日で発狂するかもしれない内容です。
本居宣長も「朱子学は理(ことわり)を重んじすぎて人の自然な感情をゆがめる」と批判し、日本人は理屈よりも「感じる心」や神道の精神を大事にすべきだと説いたそうです。
要するに私は、「理想を掲げる“道徳の学問”だと思っていたものが、生活の隅々まで規定する“ルールブック”だった」という事実に衝撃を受けたのです。自分がいかに大ざっぱに、都合よく物事を見ていたか思い知らされました。同時に、「前提がひっくり返ったとき、自分は何を思うんだろう?」という好奇心が芽生えるのも、はっきりと感じました。
矛盾した感情への戸惑い
この話をきっかけに、立て続けにもう一つ似た体験をしました。題材はアメリカの製品です。
先の話で盛り上がった後に、先方から「『アメリカ素描』という本も参考になるかもしれませんよ」と勧められ、読んでみました。そこでも思いがけない発見があります。
突然ですが、私はデニムが大好きです。色んな国の服を着ますが、とりわけアメリカの荒削りなアイテムには昔から惹かれてきました。その反面、アメリカ的な経済活動には違和感を覚えることがあります。過剰に消費を煽る(ように見える)マーケティングの姿勢は、ときに「悪しきエゴイズムの象徴」にすら思えてしまう。つまり「プロダクトは好き」だけど「経済のあり方には違和感がある」という、矛盾ともとれる二つの感情が同居していたのです。人に例えるなら「価値観は合わないのに、なぜか好き」みたいな状態で、説明のつかない気持ち悪さを覚えていました。はっきり言葉にしたのは今がはじめてですが、うん、そんな感覚があったんだと思います。
文明と文化の違い
このモヤモヤを、先の本が晴れやかにしてくれました。
「価値観が合わない」のではなく「強みの方向が違う」だけ。と、前提を捉え直すことに成功したのです。そこに導いてくれたのが、文明と文化の対比でした。
- 文明=制度や技術、合理的で普遍的な仕組み
- 文化=価値観や美意識、地域固有の習慣やつながり
本書ではアメリカと日本がこのように描かれます。(超訳しています)
- ・アメリカ=文明の象徴
移民国家で共通基盤がなかったため、合理性と普遍性が人々をまとめる力になった。契約や制度、法律といった「外的ルール」が重視される。だから「役に立つこと」「便利であること」が価値になる。ジーンズは丈夫さと自由の象徴に、ハンバーガーは万人ウケと手軽さで国境を越え、英語は「共通の道具」として広まった。 - ・日本=文化の象徴
長い共同体の歴史のなかで、外から来た文明を翻訳して文化に変えてきた。仏教は神道と融合し、漢字は日本語に溶け込み、カレーやラーメンは国民食に。祭りや方言は「合理だから残る」のではなく「空気として続く」。
個人的には、やはり服で考え進めるとわかりやすなと思いました。例えばアメリカのスウェットは動きやすさや着心地といった、合理的で普遍的な機能がアイデンティティに、また同じスウェットでも日本はブランドの思想や繊細な風合いを宿した世界観がアイデンティティになることが多い。
何かそれを経済的に反映したエビデンスはないかと調べてみると、(世界にはざっと200カ国くらいある中で)売上トップ10の50%以上がアメリカ企業で、創業年数トップ10の50%以上が日本企業だというデータに出会いました。この特徴は、文明と文化の違いを表す一つの指標のように思えました。もちろん、それだけでランキングの説明はつきませんが。
「違い」で捉える心地よさ
「超道徳と思っていたら超合理だった」とか、「価値観が合わないというより強みが違う」とか、二つの発見を通して感じたのは、「良し悪し」というより「違い」として捉えることの心地よさでした。
何かを「悪し」とすることって、余計なエネルギーを使うのかもしれません。それもあってか、「違い」をそのまま受け取る視点は、固定化した考えに解放感を生み、好奇心をかきたててくれました。これからも、前提が更新される瞬間にどんな感情が芽生えるのか、自分自身を観察していきたいと思います。
・・・ってなんかブログみたいになったwww